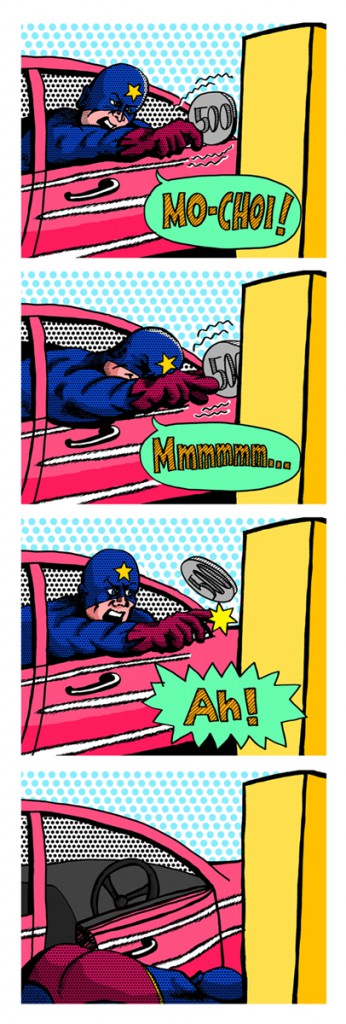友達とお茶をしながらの会話、
飲み会での話し、会議での発表、
打ち合わせなど、私のたちの生活は
伝えることで溢れています。
でも、相手の話や文章を
聞いたり読んだりする中で、
その内容が分からず、
この話しは、何に関する話しなの?
この話しは、いつまで続くの?
そんな風に思うことも、しばしば。。。
会話なら、その場で確認ができますが、
ブログやFacebookといったメディアでは
質問する人は少なく、
途中で読むのを止めてしまうケースが
ほとんどです。
そこで今回は、
話しを簡潔にまとめて分かりやすく
伝える方法についてお話します。
どんなシチュエーションでも使えますが
特に、伝えたい内容が長くなる場合に
ぜひ、活用ください。
例えば、
会議や打合わせなどの場合
1)冒頭で文章の内容、もしくは
これから話す内容を伝える。
例
『今日は、○○についてお話します』や
『先日、提案いただいた件ですが』など
2)伝える順番を伝える。
(本などの目次をイメージしてください)
例
『○○と○○の2点について、
順を追ってお伝えします』
3)説明を簡潔にして伝える。
例
『まず、○○の項目につて』
『次に、問題となる○○ですが』
『さらに、○○をするとなると○○が必要になり・・・』
『最後に、この提案については・・・』
この「まず、次に、さらに、最後に」という
流れができれば、話しがしやすく
簡潔に伝えることができます。
人は、話しのゴールが見えている方が
聞きやすく、そこに向かっていく
過程がわかると安心できるのです。
例えば、
42.195kmのフルマラソンを
イメージしてください。
いつまで走り続けるのか?と
走ることが辛くなります。
→ 1)で解決
また、コースが分からなければ
走りながら迷ってしまいます。
→ 2)で解決
ゴールとコースが分かると
どれくらいの距離を
どれくらいのペース配分で走ればいいのか
どの地点で、給水して、
どの地点から、ペースアップすればいいのか
力を入れる場所などが分かります。
それは、話す方も伝えやすく、
聞く方も聞きやすく安心できる
ということなのです。
→ 3)で解決
みなさんの文章や会話には
ゴールやコースが見えていますか?