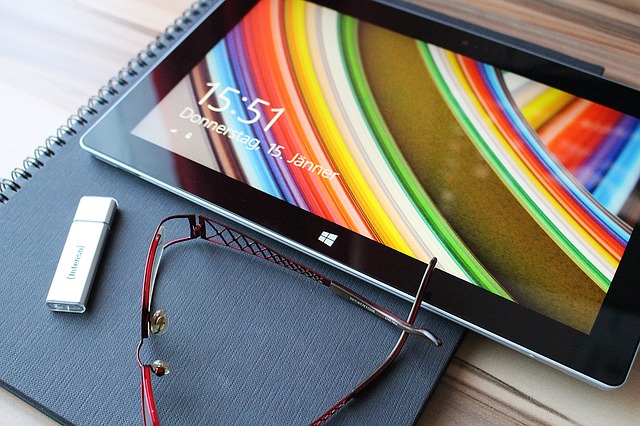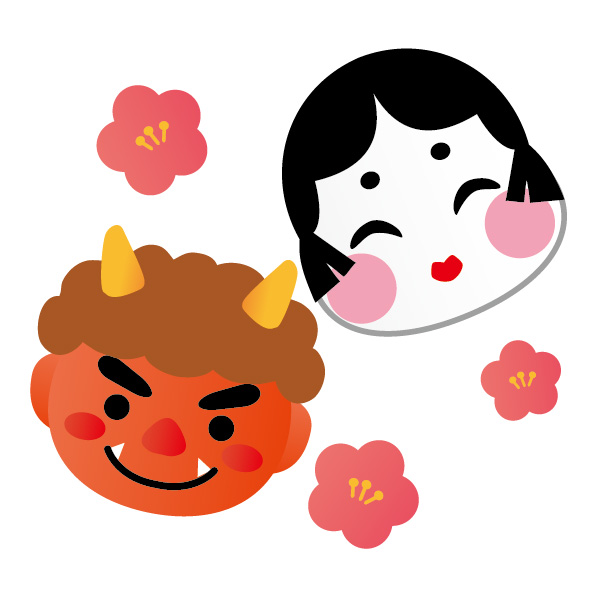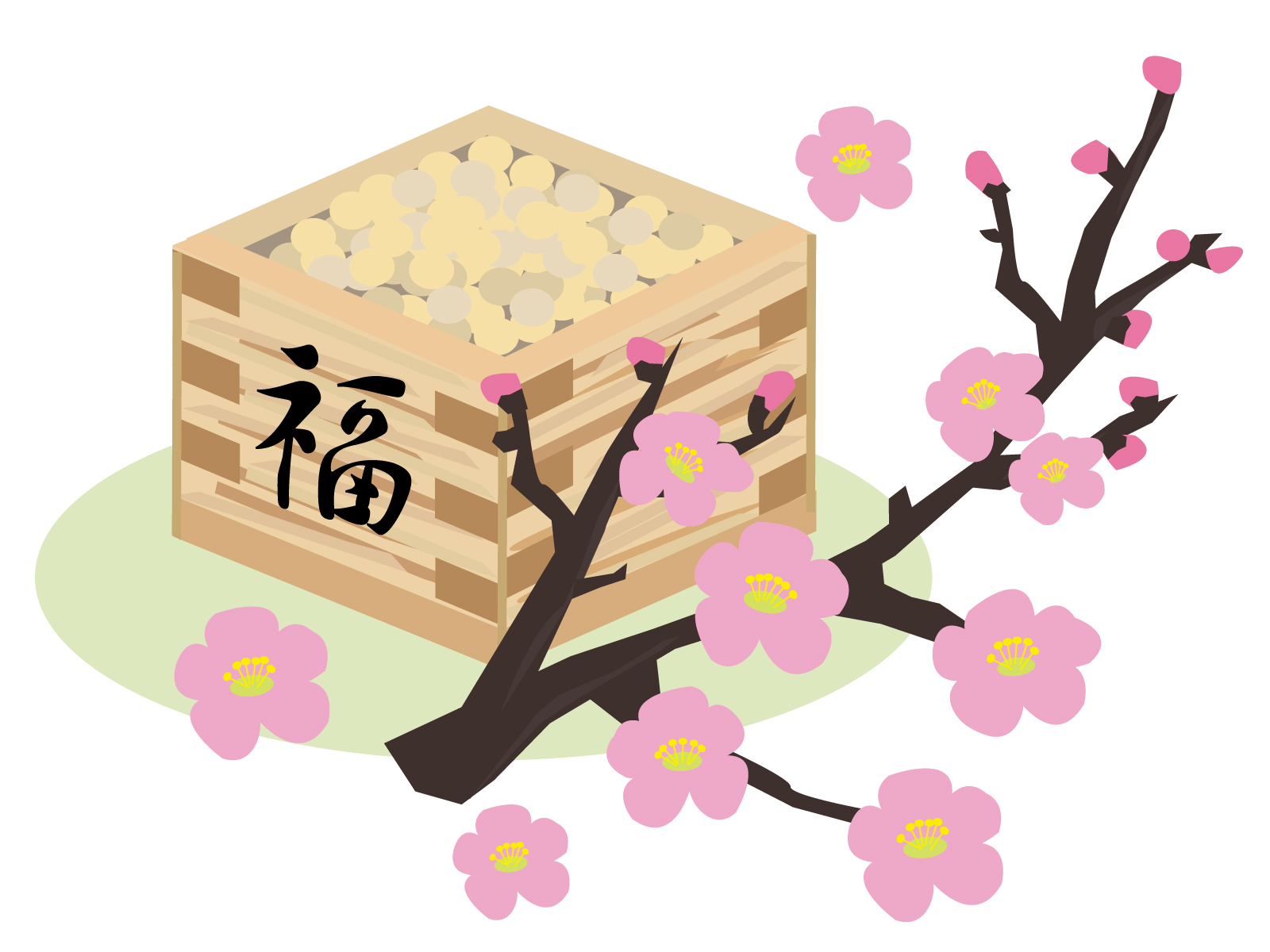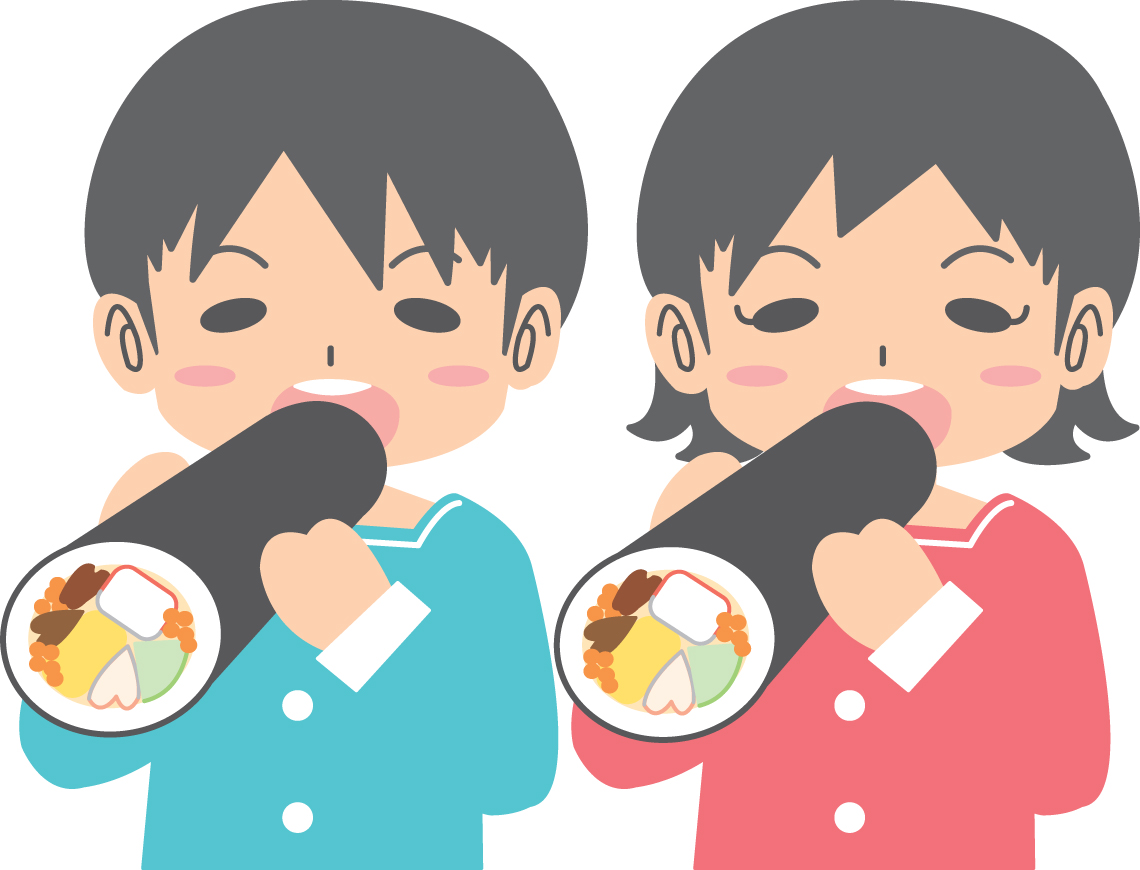メルマガやブログを書くときの悩みとして
よく耳にするのが「書くネタ」が
見つからない、というもの。
それは、「森をみて木が見えていない」
という現象かもしれません。
この説明では、少し
イメージしにくいかもしれませんが。。。
例えば
あなたが「アロマ」を使ったサービスを
提供していたとしましょう。
そこで、ブログやメルマガの
原稿のネタに困っていたとします。
そんなときは、
「アロマ」という大きな森を見ずに
項目という1つひとつの木を見ると
ネタが見つかるのです。
1つひとつの木として
(1)アロマの効能
(2)使い方
(3)サービス内容
(4)選び方
(5)楽しみ方
(6)すすめたい人
など、各項目事に
伝えたい情報を箇条書きで、
書き出してみてください。
書き出せたら
まずは、(1)単体で
テーマを1つ決めて、1つ記事を書く。
次に、(1)と(2)を組み合わせて
テーマを1つ決めて、1つ記事を書く。
その次は、(1)と(2)と(3)を
組み合わせて
テーマを1つ決めて、1つ記事を書く。
:
:
これを続けると、
(1)を軸とした組み合わせが6通りできます。
ということは、
これで6つのネタ(原稿)が出来ます。
(2)単体および(2)を軸にした組み合わせ
(3)単体および(3)を軸にした組み合わせ
(4)単体および(4)を軸にした組み合わせ
:
:
を続けていくと、、、
え〜と、何通りかな〜。。。。σ(^◇^;)
学生時代の数学の時間みたいだな〜。
あははは(苦笑)
こうやって、色んなパターンで
組み合わせていくと
かなり、たくさんのネタができるんですよ!!
文章は、国語の分野だと思いがちですが
こうすれば、こうなる!
という数学的、物理的な思考も必要なのです。
(⌒∇⌒)ノ
みなさんも、ぜひやってみてくださいね!