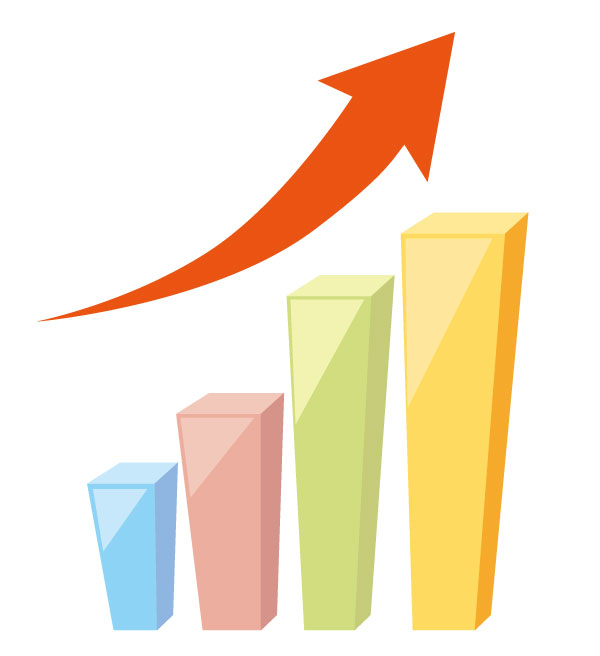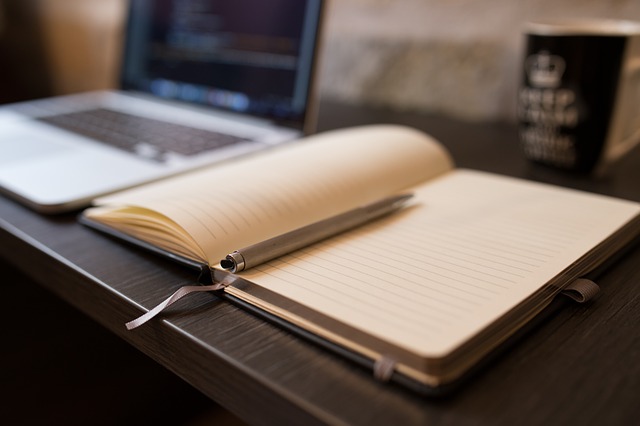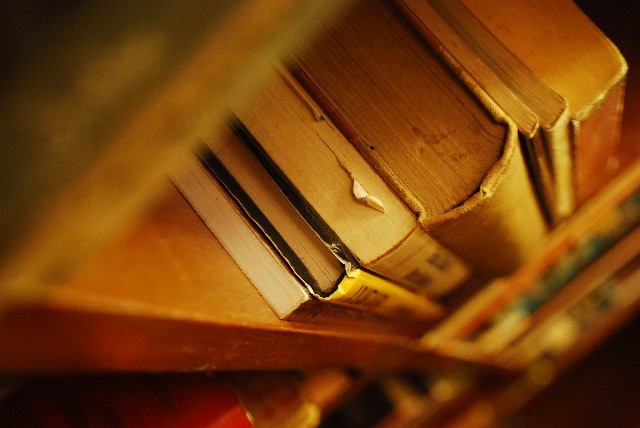反応を上げたいと思って一生懸命、
文章を書いているのに、
アクセス数や反響が伸びない。
そんな悩みを聞くことがあります。
原因は、いくつかあるのですが。。。
今回は、その改善策の一例をご紹介します。
まず、注目すべきことは
<冒頭の書き出し>です。
読み始め(冒頭)で、
書かれている内容に、興味が湧かなければ
その先の文章で、
どんなに良いことが書かれていても
読まれる確率は下がります。
例えば、
みなさんは、次の<A>と<B>
どちらの文章の続きが読みたいですか。
また、どちらの販売会に行きたいですか。
<A>
○ ○地方で採れる美味しい野菜を
販売している○○会社です。
○ 月○日から、新鮮野菜のチェック方法とともに
その日の朝に収穫した、新鮮な野菜を
販売したいと思います。
みなさん、ぜひお越しください。
場所は・・・
<B>
○ ○地方で採れる美味しい野菜を
販売している○○会社です。
食品の安全について注目されることが多い昨今。
みなさんは、何を基準に野菜を選んでいますか。
実は、体の健康を考えた
野菜の選び方や見た目では分からない
鮮度のチェックの仕方があるんですよ。
その方法を○月○日から行う販売会で
実際に野菜を見ながら
お話ししたいと思います。
と言いつつ、
それまで待てない方もいると思うので
少しだけお話しすると・・・
さて、みなさんは<A>と<B>の
どちらの販売会に行きますか。
たぶん<B>ですよね。
なぜ、そうなるのか。
<A>について
新鮮野菜のチェック方法、と
いきなり言われても戸惑いますよね。
もしかしたら、そんな情報いらないから
新鮮な野菜だけ買いたいわ。
って言う人もいるかも知れません。
書き手の伝えたいことが伝わっていませんし
読み手の興味も薄々です。
<B>について
まず、食の安全性、野菜選びの基準は?と
世の中の動きとともに、
問題提起をしています。
→ 確かにそうね、と読み手の同意を得ます。
チェックの仕方があります、と
解決策を提示しています。
→ そんな方法があるんだ、知りたい!と
情報を与えるキッカケを作ります。
その方法は、と続いています。
→ 何なに、と興味津々になります。
話しの筋道をつけて
順に文章を構成することで読みやすくなり
次の一文が読みたくなります。
そうすると、最後まで読んでもらえる
確率が上がり反響もアップしやすくなるのです。
みなさんも、ぜひやってみてくださいね。
<あわせて読みたい関連記事>